プロジェクトの遅延を防ぐための代表的な手法として知られる「クリティカルチェーン法」。
制約理論(TOC)を応用したこの考え方は、クリティカルパス法に比べてリソース制約や人間の行動特性を考慮している点で大きな特徴があります。
本記事では、クリティカルチェーン法の概要や特徴を解説するとともに、PMBOKの各版でどのように扱われてきたのかを比較します。
目次
提唱者・出典
- 提唱者:Eliyahu M. Goldratt
- 初出:1997年『Critical Chain』(日本語訳されたものがダイヤモンド社から出版されています)
- 背景:ゴールドラットは「制約理論(TOC:Theory of Constraints)」の提唱者。
製造業のボトルネック管理をプロジェクトマネジメントに応用したのがクリティカルチェーン法(Critical Chain Method, CCM)。
クリティカルチェーン法の概要
目的
プロジェクトの遅延を防ぎ、納期を守ること。
基本的な考え方
– クリティカルチェーンは「リソース制約を考慮した最長経路」
– 各タスクに余裕を持たせず、プロジェクト全体にバッファを配置することで遅延を吸収する
バッファの種類
プロジェクトバッファ:クリティカルチェーンの末尾に置き、全体の遅延を吸収
フィーディングバッファ:非クリティカルチェーンが合流する前に置き、遅延の伝播を防ぐ
リソースバッファ:重要リソースの直前に置き、準備不足を防止
PMBOKにおける扱いの変遷
| PMBOK版 | 位置づけ |
|---|---|
| 第3版 (2004)~第5版 (2013) | スケジュール作成の技法の1つとして定義されていた。 CPMとの比較され、「フィーディングバッファ」、「プロジェクトバッファ」の説明があった。 |
| 第6版 (2017) | 「バッファ」や「スケジュール予備」の説明は残るが、Critical Chain Methodという見出しは削除された。 |
| 第7版 (2021) | 個別手法の列挙は縮小され、明示的言及はほぼなし。 |
第6版では「クリティカルチェーン法」という名称が消えた一方で、そのアイデアは残っています。
従来手法との違い
クリティカルパス法(CPM)
- 作業の依存関係と所要時間のみを考慮
- リソース制約は考慮されず、現実との乖離が生じやすい
クリティカルチェーン法(CCM)
- リソース制約を考慮し、現実的な計画を作成
- 各タスクに余裕を置かず、プロジェクト全体にバッファを配置
- パーキンソンの法則や学生症候群を防ぐ設計
まとめ
クリティカルチェーン法は、制約理論をプロジェクトマネジメントに応用した手法です。
特にPMBOKにおいては第6版以降明示的な言及がなくなりましたが、その考え方はシステム開発含む製造業で現在も有効です。
また、プロジェクトマネージャ試験では内容を問われ続けていますので、PMを受験する方はぜひ考え方をおさえておきたいところです。
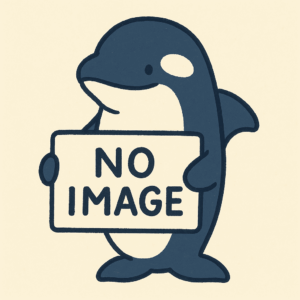
コメント